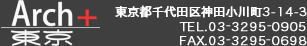2023.07.18
99.東京の緑のネットワーク


日本青年館最上階16階のラウンジから母校都立青山高校(右)神宮球場(左)を見下ろす。
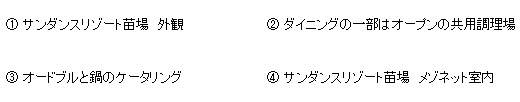
昨年の5月に高校の同期会が行われた。卒業してから52年目の春であった。当初は卒業後50年目(半世紀!なんという長い年月)に際して、卒業式など何もなく卒業した我々(ヤチダヨリ#58.アオコウ卒業の頃参照)の一部の有志が50年前を偲ぼうという集まりであった。しかし、時のコロナ禍のため1年、2年と延び、ようやく1年前に開かれた。場所は日本青年館、以前は1925年に建てられたレトロな建物であったが、1977年に一度建て替えられ、人気のホールも併設された。しかし、2021年の東京オリンピックで国立競技場の建て替えに伴い、場所を変え、母校に隣接する敷地に2017年に移転して建てられた。日本スポーツ振興センター(JSC)と一体的に整備され、地上16階、延べ床面積3万㎡の巨大建築となった。会場は最上階16階の宴会場であった。ロビーを通過すると母校と神宮球場が見えてきた。参加者は77名。2011年と2016年にも同期会があったので、同じような顔ぶれでもあったが、コロナ禍が終わったわけでないので、前回の参加者が必ずしも出席しているわけでなく、新しく見かける人も多かった。年のせいか、亡くなった人もふえてきた。リタイアしている人が多く、昔の話、持病の話、孫の話などで花が咲いた。また、女性はいつまでも元気なのが目立っていた。
入学当時は、世田谷の田舎中学(当時の世田谷桜丘近辺は畑も多く渋谷・新宿から比べると大田舎であった)から都会の高校に来た感があり、整った都市景観の中で何か大人になった気分を感じた。高校のグランドはいろいろな運動部が共用するため。絵画館を周回するランニングや銀杏並木でのうさぎ跳び(当時は観光客などほとんどいなかった)時として明治公園での練習などに周辺を使用した。また、美術の授業で周辺の風景を描くことになり、絵画館前の銀杏並木が人気を博した。ただ、高層ビルは建っておらず。校門の目の前には、東京ボウリングセンター(現TEPIAあるところ、当時からいろいろなゲームや飲食があり、遊びの殿堂であった。)やレストラン外苑があったが、ほとんどが平屋か2階建てであった。1969年に吉村順三設計の青山タワービルが建てられたころから高層化が進んだ。その前はのんびりした住宅街であった。表参道も人通りはあまりなく、同潤会青山アパートもひっそりとして建っていた。
明治神宮外苑再開発で神宮球場や秩父宮ラグビー場が建て替えられる。2028年までに明治神宮第2球場と周辺の緑地に全天候型のラグビー場をつくる。2032年までに秩父宮ラグビー場と神宮球場と会員制テニスクラブのところにホテル併設型の野球場と野球場に接続した商業施設を完成させるようだ。その後2036年までに中央広場とオフィスと室内運動場とスポーツ関連宿泊施設を完成させるといわれている。敷地の大半は少し離れた地にある明治神宮が所有している。そこに大手商社・大手不動産会社・スポーツ関連の独立行政法人が絡んだ事業である。東京でも屈指の人気のある地域での利権が絡んだ巨大プロジェクトである。樹木の伐採などをめぐり故坂本龍一氏や村上春樹氏ら同世代の文化人の人達が反対を表明している。しかし、手続き上、このまま開発が進むであろう。1926年につくられた明治神宮球場は、我々が入学したころすでに相当古かった。それから55年。月日が経つのも早いものである。
先日、北海道の北広島に完成したエスコンフィールドHOKKAIDOで野球観戦をしてきた。広大な敷地に神殿のような構えで、アメリカ大リーグで発祥したボールパークのコンセプトそのままである。広大な敷地での人の集まる開放的な都市的空間は確かに素晴らしかった。しかし札幌から相当に離れた人口5万人の都市での新しい試みである。明治神宮外苑再開発とは対極的な環境であった。神宮の森は、都心での貴重な樹木ではある。しかし局所的な樹木の保存にこだわらず、植生が豊かである東京では、神宮外苑を中心として東に東宮御所、外堀、皇居、北に新宿御苑、西に明治神宮、代々木公園、南に青山霊園などにつなぐように増やし、それを少しずつ、開放して行けば、世界中の都市にも稀なほど豊かな緑のネットワークとなるはずである。
入学当時は、世田谷の田舎中学(当時の世田谷桜丘近辺は畑も多く渋谷・新宿から比べると大田舎であった)から都会の高校に来た感があり、整った都市景観の中で何か大人になった気分を感じた。高校のグランドはいろいろな運動部が共用するため。絵画館を周回するランニングや銀杏並木でのうさぎ跳び(当時は観光客などほとんどいなかった)時として明治公園での練習などに周辺を使用した。また、美術の授業で周辺の風景を描くことになり、絵画館前の銀杏並木が人気を博した。ただ、高層ビルは建っておらず。校門の目の前には、東京ボウリングセンター(現TEPIAあるところ、当時からいろいろなゲームや飲食があり、遊びの殿堂であった。)やレストラン外苑があったが、ほとんどが平屋か2階建てであった。1969年に吉村順三設計の青山タワービルが建てられたころから高層化が進んだ。その前はのんびりした住宅街であった。表参道も人通りはあまりなく、同潤会青山アパートもひっそりとして建っていた。
明治神宮外苑再開発で神宮球場や秩父宮ラグビー場が建て替えられる。2028年までに明治神宮第2球場と周辺の緑地に全天候型のラグビー場をつくる。2032年までに秩父宮ラグビー場と神宮球場と会員制テニスクラブのところにホテル併設型の野球場と野球場に接続した商業施設を完成させるようだ。その後2036年までに中央広場とオフィスと室内運動場とスポーツ関連宿泊施設を完成させるといわれている。敷地の大半は少し離れた地にある明治神宮が所有している。そこに大手商社・大手不動産会社・スポーツ関連の独立行政法人が絡んだ事業である。東京でも屈指の人気のある地域での利権が絡んだ巨大プロジェクトである。樹木の伐採などをめぐり故坂本龍一氏や村上春樹氏ら同世代の文化人の人達が反対を表明している。しかし、手続き上、このまま開発が進むであろう。1926年につくられた明治神宮球場は、我々が入学したころすでに相当古かった。それから55年。月日が経つのも早いものである。
先日、北海道の北広島に完成したエスコンフィールドHOKKAIDOで野球観戦をしてきた。広大な敷地に神殿のような構えで、アメリカ大リーグで発祥したボールパークのコンセプトそのままである。広大な敷地での人の集まる開放的な都市的空間は確かに素晴らしかった。しかし札幌から相当に離れた人口5万人の都市での新しい試みである。明治神宮外苑再開発とは対極的な環境であった。神宮の森は、都心での貴重な樹木ではある。しかし局所的な樹木の保存にこだわらず、植生が豊かである東京では、神宮外苑を中心として東に東宮御所、外堀、皇居、北に新宿御苑、西に明治神宮、代々木公園、南に青山霊園などにつなぐように増やし、それを少しずつ、開放して行けば、世界中の都市にも稀なほど豊かな緑のネットワークとなるはずである。
Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可