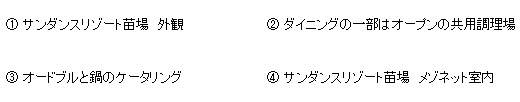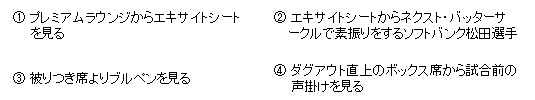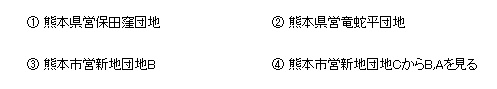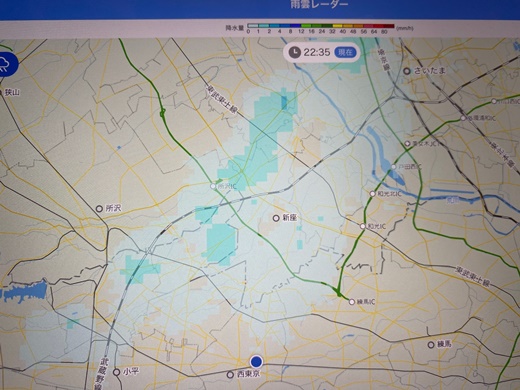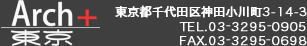2024.01.11
100.ブラジル大旅行


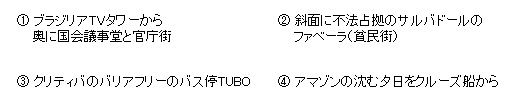
昨年の8月から9月にかけて、「アルゼンチン・ブラジル建築・都市・文化を巡る旅」に参加した。建築家の南條洋雄さんが企画された旅行で、建築関連の設計者、編集者、研究者とその家族総勢20名の旅行となった。その南條さんとは2018年のスペインポルトガル旅行以来、懇意にしていただき、2020年にブラジル旅行をかねてから予定し、楽しみにしていた。しかし、世界的パンデミックの影響で延期され、三年越しの待望の旅行となった。南條さんは1975年から1985年までブラジルで活動され、1985年より日本に戻り、南條設計室を主宰しておられる。ブラジルの建築界の要人との交流も深く、今まで多くの日本の建築関係者をブラジルに案内してきた。いわばブラジルと日本の建築界の橋渡しをやってこられた方である。久しぶりで最後の案内であるといっておられる。現地の事情に精通されているので、すべてお任せの旅であった。せっかく行くならとアルゼンチンのブエノスアイレスやイグアスの滝、アマゾンなどの観光名所も加わり、建築、都市、自然、生活、文化と大変内容の幅の広く深い充実した20日間の旅となった。
ポルトガル領ブラジルの最初の首都はサルバドールであった。砂糖産業により栄え、農園の労働力確保のため多くの黒人がアフリカから奴隷として連れてこられた。彼らの音楽、踊り、宗教、料理など様々な文化がこの地にもたらされ、融合し、独特なアフロ・ブラジル文化として花開くことになった。その影響から黒人の割合が多い。ここでは発祥の地とされるサンバとカポエイラのショーを見た。街の広場では、バテリア(打楽器隊)が昼と夜となく響き渡っていた。
そののちに首都になったのが、リオ・デ・ジャネイロで、農産物、金、ダイアモンドの輸出で発展し、サルバドールにかわりブラジルの首都となった。1960年のブラジリア遷都まで続いた。カーニバルが有名だが、独特の変化にとんだ地形で「山と海との間のカリオカの景観群」で世界遺産になっている観光都市でもある。かつてはアフリカからの奴隷の到着地であった負の遺産の港湾地区も、オリンピックやFIFAワールドカップで再開発がなされ大分治安もよくなったといわれる。
その次がブラジリアである。内陸部の発展のためにかねてより検討されていたブラジルの首都移転によって生まれた都市である。1955年から1960年まで極めて短期間になされ、世界にも稀に見る遷都であった。当初は2000年に人口60万人という予測であったが、現在、周辺の衛星都市を加えると300万人の人口を有し、自動車は100万台もある。機能的につくられた交通システムも通勤時には大渋滞していた。都市の機能をゾーニングによって計画し、短期につくられた実験的な都市である。その界隈性の欠如から賛否両論というより、否の方が大勢を占めることが多いが、派生した生活像は近未来なのか、時代遅れなのか?
クリティバは、1970年代から計画的な街づくりを行ってきた都市でゴミの問題からリサイクル、環境都市交通システムまで環境都市として世界的に知られている。特に専用レーン、多連結のバス、チューブ型のバリアフリーのバス停などを用い、日常の市民の足として使われている。住民の多くは、ヨーロッパからの移民でブラジルの中では富裕な都市である。
アマゾン地域の中心都市マナウスは、コロンビア源流のネグロ川とアマゾン本流が合流する地点にある。19世紀末ゴムの生産で黄金期を迎えた。アマゾンは世界最長の川だが、川幅広く、水深も深いため、遠洋航海用の船も上流まで航行できる。そのため規制緩和を受け、世界中の企業が進出し、工業都市としても発展した。雨季と乾季の水位が激しく、気候変動の影響を最も多く受けるのではないかといわれている。ここでは外洋のような大河からピラニアの生息するジャングルまでクルーズを楽しんだ。
最後に訪れたサンパウロは、南米最大の都市である。それだけに貧富の差を感じた都市であった。これがブラジルの縮図でもあるように思えた。ブラジルの各都市は、混血を含めた多様な人種構成、貧富の差、思い切った政策、また建築デザイン、都市の成り立ち、それぞれ異なるが、島国日本とは違うダイナミズムに近未来の社会を先取っているような気もした。
2019年に行ったスイス旅行(ヤチダヨリ#87.スイスの食堂車、#90.モントルー・ジャズ・フェスティバル2019参照)は最後の大旅行だと思っていたが、今回も二度目の大旅行となってしまった。ただ、これからも旅を続けたい。しかし、今回のようにジェット機で飛び回る旅行ではなく地を這うような旅として行こうと思っている。
ポルトガル領ブラジルの最初の首都はサルバドールであった。砂糖産業により栄え、農園の労働力確保のため多くの黒人がアフリカから奴隷として連れてこられた。彼らの音楽、踊り、宗教、料理など様々な文化がこの地にもたらされ、融合し、独特なアフロ・ブラジル文化として花開くことになった。その影響から黒人の割合が多い。ここでは発祥の地とされるサンバとカポエイラのショーを見た。街の広場では、バテリア(打楽器隊)が昼と夜となく響き渡っていた。
そののちに首都になったのが、リオ・デ・ジャネイロで、農産物、金、ダイアモンドの輸出で発展し、サルバドールにかわりブラジルの首都となった。1960年のブラジリア遷都まで続いた。カーニバルが有名だが、独特の変化にとんだ地形で「山と海との間のカリオカの景観群」で世界遺産になっている観光都市でもある。かつてはアフリカからの奴隷の到着地であった負の遺産の港湾地区も、オリンピックやFIFAワールドカップで再開発がなされ大分治安もよくなったといわれる。
その次がブラジリアである。内陸部の発展のためにかねてより検討されていたブラジルの首都移転によって生まれた都市である。1955年から1960年まで極めて短期間になされ、世界にも稀に見る遷都であった。当初は2000年に人口60万人という予測であったが、現在、周辺の衛星都市を加えると300万人の人口を有し、自動車は100万台もある。機能的につくられた交通システムも通勤時には大渋滞していた。都市の機能をゾーニングによって計画し、短期につくられた実験的な都市である。その界隈性の欠如から賛否両論というより、否の方が大勢を占めることが多いが、派生した生活像は近未来なのか、時代遅れなのか?
クリティバは、1970年代から計画的な街づくりを行ってきた都市でゴミの問題からリサイクル、環境都市交通システムまで環境都市として世界的に知られている。特に専用レーン、多連結のバス、チューブ型のバリアフリーのバス停などを用い、日常の市民の足として使われている。住民の多くは、ヨーロッパからの移民でブラジルの中では富裕な都市である。
アマゾン地域の中心都市マナウスは、コロンビア源流のネグロ川とアマゾン本流が合流する地点にある。19世紀末ゴムの生産で黄金期を迎えた。アマゾンは世界最長の川だが、川幅広く、水深も深いため、遠洋航海用の船も上流まで航行できる。そのため規制緩和を受け、世界中の企業が進出し、工業都市としても発展した。雨季と乾季の水位が激しく、気候変動の影響を最も多く受けるのではないかといわれている。ここでは外洋のような大河からピラニアの生息するジャングルまでクルーズを楽しんだ。
最後に訪れたサンパウロは、南米最大の都市である。それだけに貧富の差を感じた都市であった。これがブラジルの縮図でもあるように思えた。ブラジルの各都市は、混血を含めた多様な人種構成、貧富の差、思い切った政策、また建築デザイン、都市の成り立ち、それぞれ異なるが、島国日本とは違うダイナミズムに近未来の社会を先取っているような気もした。
2019年に行ったスイス旅行(ヤチダヨリ#87.スイスの食堂車、#90.モントルー・ジャズ・フェスティバル2019参照)は最後の大旅行だと思っていたが、今回も二度目の大旅行となってしまった。ただ、これからも旅を続けたい。しかし、今回のようにジェット機で飛び回る旅行ではなく地を這うような旅として行こうと思っている。
Copyright(c) 谷内田章夫 無断転載不可